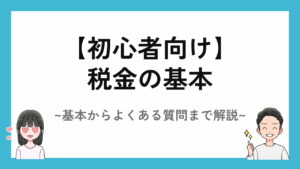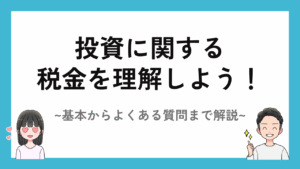将来の生活の安心を支える年金ですが、その仕組みや受け取り方は意外と複雑で、よくわからないままの人も多いです。
本記事では、年金の基本的な仕組みや種類、受給開始年齢、受け取れる金額の目安など初心者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。これを読めば、年金の全体像がつかめて、将来の資金計画も立てやすくなりますよ。
年金の基本知識
まずは年金の基本的な仕組みや受け取り方など、初心者が押さえておきたい基本ポイントを紹介します。
年金は3階建て
| 年金 | 対象者 |
|---|---|
| ①国民年金(基礎年金) | 20歳以上の全国民(扶養内の主婦含む) |
| ②厚生年金 | 主に会社員・公務員 |
| ③私的年金(iDeCo・企業年金など) | 任意加入 |
日本の年金制度は「3階建て」で、国民年金(基礎年金)、厚生年金、私的年金(iDeCoなど)があります。国民年金は全員が加入しており、扶養内の主婦も年金は払っていませんが①国民年金はもらえます。
また②厚生年金は会社員のみ対象で、自営業は関係ありません。そのため③私的年金が用意されており、最近ではiDeCoや企業型確定拠出年金を活用するケースが多いです。
受け取り開始は基本的に65歳
現在の年金は、原則として65歳から受け取りを開始します。
ただし「もっと早く受け取りたい」「もう少し遅らせて増やしたい」といった希望がある場合は、繰り上げ受給や繰り下げ受給という制度もあります(後半の章で詳しく説明します)。
受け取れる金額は納めた金額に比例する
年金は、単に年齢に達したら自動でもらえるお金ではありません。どれだけ長く、きちんと保険料を納めたかによって、将来もらえる年金額が決まります。
- 国民年金:保険料の納付月数(最長480カ月=40年)で決まる
- 厚生年金:給与(報酬)と加入年数に応じて決まる
つまり、「若いころからしっかり納めていた人」「高い収入で長く会社に勤めた人」は年金額が多くなりやすいです。
繰り上げ・繰り下げで年金額が変動する
年金の受け取り時期は、早める(繰り上げ)ことも、遅らせる(繰り下げ)ことも可能です。そのタイミングによって、受け取る金額が増減します。
- 繰り上げ受給(60〜64歳):1カ月早めるごとに年金が0.4%減額
- 繰り下げ受給(66〜75歳):1カ月遅らせるごとに年金が0.7%増額
たとえば70歳まで受給を繰り下げれば、一生涯受け取る年金額が約42%アップします。長生きする自信がある人は繰り下げを選ぶことで、トータルで得する可能性もあるんです。
保険料の仕組みと納付のルール
国民年金と厚生年金では保険料の計算や納め方が異なります。意外と年金の仕組みを理解していない人が多いので、保険料の仕組みやルールを初心者向けに解説します。
国民年金の保険料は固定
国民年金の保険料は全国一律の定額制で、令和7年度は1か月17,510円です(毎年異なり、年々増額しています)。
主に自営業者、フリーランス、学生が対象で、扶養内の主婦は年金の支払いはしませんが国民年金の受け取り対象者です(会社員は厚生年金の支払いに含まれています)。
受け取れる金額は20~60歳まで40年間納めた場合で約80万円/年。ただし40年間納めていない場合は、割合に応じて減額されます。例えば20年間しか納めていない場合は半分の40万円/年です。
厚生年金は給料に応じて決まる
厚生年金は会社員や公務員が加入する制度で、保険料は毎月の給与と賞与を基に計算されます。具体的には「標準報酬月額」と「標準賞与額」に保険料率(約18.3%)をかけ、その半分を会社、半分を従業員が負担します。
収入が高いほど保険料も高くなり、その分将来受け取れる年金額も増えます。また、厚生年金に加入している間は国民年金の保険料も支払っている扱いとなるため、もらえる年金は国民年金+厚生年金です。
受け取れる金額は国民年金は最大で約80万円/年、厚生年金は納付期間の平均年収が500万円なら約110万円/年なので合計約190万円/年の年金が受け取れます(正確ではないため、およその目安としてお考え下さい)。
扶養内なら1円も納めずに国民年金がもらえる
配偶者が厚生年金に加入している場合、一定の収入条件を満たす専業主婦(主夫)やパート勤務者は「第3号被保険者」として、自分で国民年金の保険料を納める必要がありません。
この制度により、保険料を払っていなくても国民年金の被保険者としてカウントされるため、正直コスパは最強です。ただし、扶養内で働くとなると収入を抑える必要があるため、配偶者の収入が相当多くないと難しいのが現実です。
未納があると年金が減る
保険料を支払わなかった期間(未納)があると、その分将来受け取れる年金額が減ります。年金受給のためには原則として10年以上の納付期間が必要です。また未納期間が長いと、障害年金や遺族年金の受給資格を失う可能性があります。
納付が難しい場合は免除や猶予制度を利用し、できるだけ未納期間を減らすことが大切です。追納制度を活用すれば、過去の未納分を後から納めて年金額を回復できます。
もらえる年金額の目安と計算方法
年金の受給額は加入期間や納付額によって変わるため、自分がどれくらいもらえるのか把握しておくことは重要です。国民年金と厚生年金の計算方法の概要や、年金定期便を使った確認方法を詳しく解説します。
国民年金はいくらもらえる?
国民年金は基礎年金とも呼ばれ、20歳から60歳までの40年間保険料を満額納付した場合、令和7年度で年間約83万円が支給されます。
ただし、40年間納めていない場合は未納期間に応じて減額されます、例えば30年間なら83万×3/4=約62万円、20年間なら83万×1/2=約41万円です。
厚生年金はいくらもらえる?
厚生年金の受給額は、簡単に言うと加入期間の平均年収で計算できます。下記の計算式に当てはめて計算してみてください。
たとえば、平均年収が500万円で40年間加入した場合、厚生年金部分だけで年間約110万円の受給が見込まれます。国民年金の基礎年金と合わせると、合計で約190万円程度となります。ただし、実際の計算は個々の加入歴や給与額で変わるため、あくまで目安です。
厚生労働省のシミュレーションツールも便利
厚生労働省が公表している「公的年金シミュレーター」を使えば、サクッと計算できます。ぜひ活用してみてくださいね。
何歳からもらうのが得?
年金は原則65歳から受け取れますが、60歳から繰り上げて受給することも、66歳以降に繰り下げて受け取ることも可能です。「何歳からもらうのが得か?」と疑問を持つ方が多いですが、正解は人によって異なります。
早く受け取れば生活資金に余裕ができますが、受給額は減少します。一方で繰り下げると受給開始は遅くなりますが、月々の受給額は増加します。そのため「いつまで生きるか?」という寿命の予測がカギになります。
繰り上げ受給(60〜64歳)の仕組み
繰り上げ受給を選ぶと、1か月早めるごとに0.4%ずつ減額されます。もし60歳から受け取る場合は60か月×0.4%で24%の減額となります。一度繰り上げて受給を始めると、その後の年金額は一生その減額されたままです。
いつまで生きるかわからないから早く年金を受け取りたい人や、自分で運用できる人におすすめ。
繰り下げ受給(66〜75歳)の仕組み
繰り下げ受給を選ぶと、1か月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。もし75歳から受け取る場合は120か月×0.7%で84%の増額となります。
ただし、受給するまでの生活費が十分に準備できていないといけません。また、長生きできなければ結果的に早く受け取っておけばよかったと後悔するケースもあるので慎重に検討しましょう。
損益分岐点は何歳?
損益分岐点は、繰り上げ受給の場合は約80歳、繰り下げ受給の場合は約86歳です。80歳まで生きられないと思うなら繰り上げ、86歳より長生きできると思うなら繰り下げがお得です。
ただし、単なる損得で選ぶのはおすすめしません。自分の状況やライフプランに合わせて決めるのがベストです。
受給タイミングを考えるポイント
年金受給のベストタイミングは人それぞれです。下記のポイントを考慮して、自分にとって最適なタイミングを考えてみてください。
- 健康寿命
- 貯蓄状況
- 就労状況
もし、寿命が長く、貯蓄もたくさんあり、70歳まで働くなら繰り下げしても良いです。一方で、貯蓄が少なく生活に困るならすぐにでも年金を受給した方が良いケースもあります。損得だけでなく、自分がどうしたら後悔しないかも合わせて検討しましょう。
-2-300x169.png)
年金に関するよくある疑問と不安
他にもお得情報を発信しているので、ぜひ参考にしてくださいね!
私たちはお得と株が大好きなズボラ夫婦で、投資やポイ活情報など誰でもできる資産形成を発信中。お金を増やしたい、お得に生活したい人はぜひフォローしてね♪
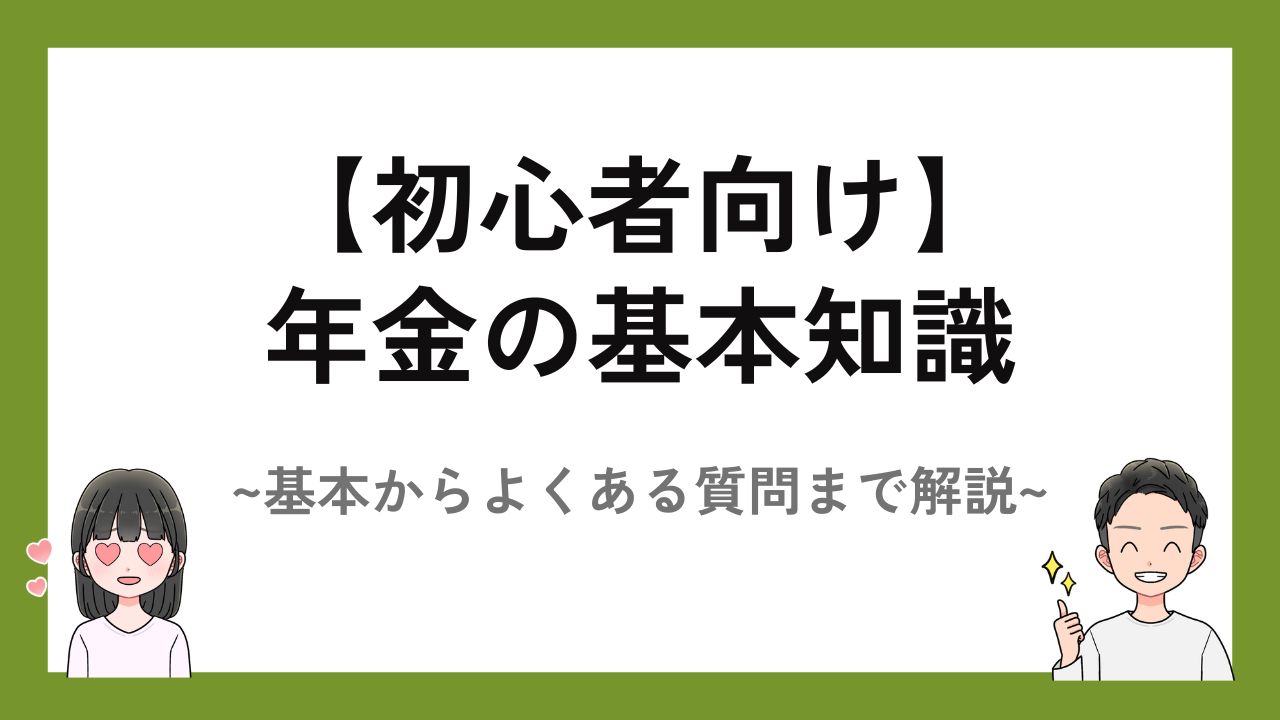
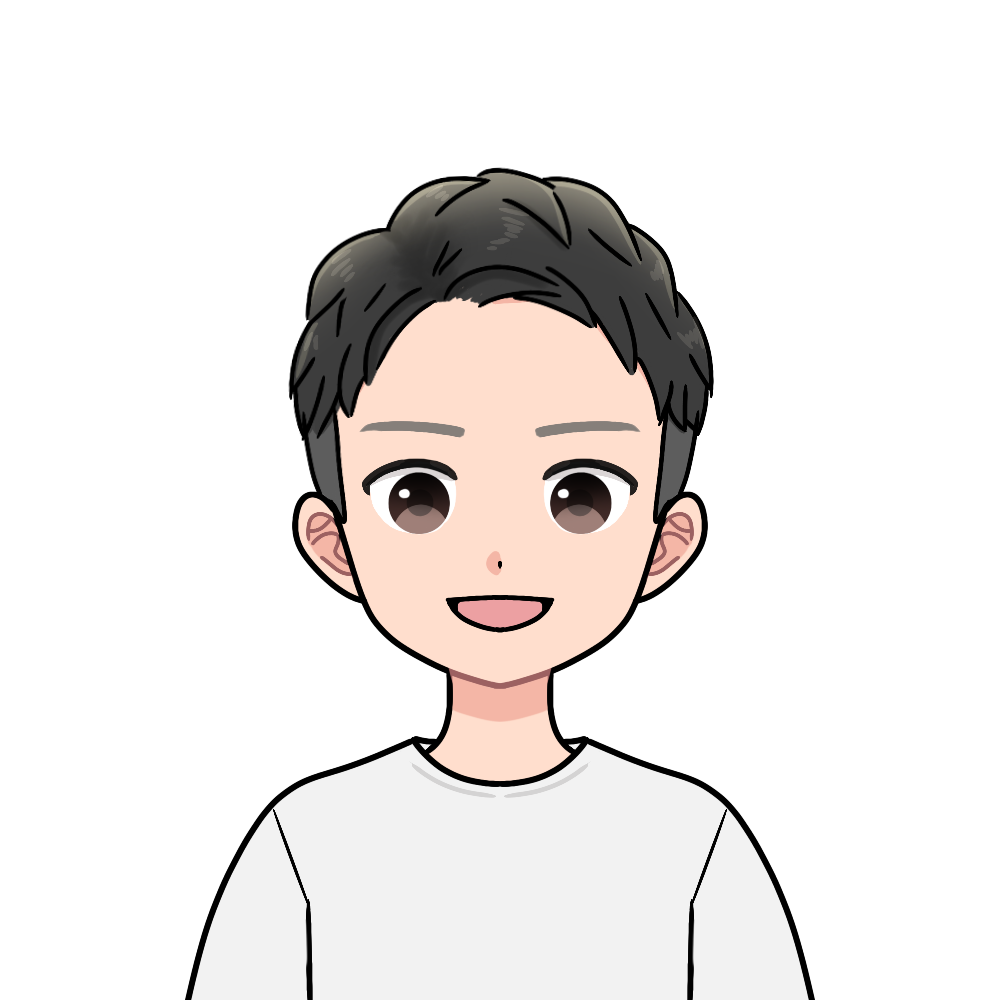
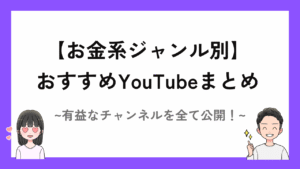
-1-300x169.png)
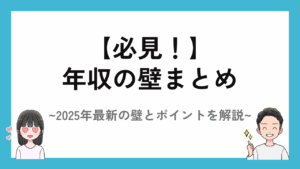
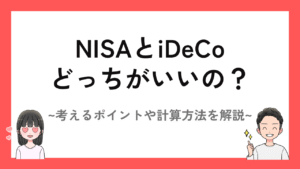
-300x169.png)