お金を増やしたいと思って投資を始めたのに、なぜか成果が出ない。むしろ損をしてしまった…という方の多くは「資産形成のNG行動」を知らずにやってしまっていることが原因です。
この記事では、初心者が特につまずきやすい9つの落とし穴と、回避法をわかりやすく解説します。これから投資を始める人も、すでに始めている人も、ぜひチェックしてみてください。
銀行でNISA、iDeCoを始める
投資を始める時に「相談できるから銀行の窓口に行こう」と思う方は多いですが、絶対にダメです。銀行では取り扱える商品の種類が限られており、信託報酬(運用コスト)が高い投資信託を勧められる場合が多いです。
例えば同じオルカンの投資信託でも、楽天やSBI証券ならコストが0.1%以下で買えますが、銀行だと0.5%~1%のコストがかかるオルカンを勧められるケースも。。手数料の差は20年、30年と積み上がると大きな金額になります。
回避法:
- NISAやiDeCoはネット証券から始める
- どうしても銀行で始めたいならコストを比較する
投資代行サービスに運用を任せる
「プロに任せれば安心」と思い、ロボアドバイザーやファンドラップに投資を丸投げする人も増えています。確かに手軽さは魅力ですが、年間1~3%の手数料がかかる場合もあり、長期投資では大きなコストになります。
例えば年5%の運用益でも、手数料3%が引かれれば実質2%にしかなりません。20年後には数百万円の差になることもあります。今の時代は自分で簡単に運用できるので、人に任せるのは避けましょう。
回避法:
- 自分でオルカンやS&P500を運用する
- 利用する時はコストや投資方針をしっかり理解する
目的を決めずに投資を始める
「とりあえず資産を増やしたい」と目的が曖昧なまま投資を始めると、下落時に不安になって売ってしまったり、逆に上がった時に勢いで買い増したりと感情に振り回されがちです。
また、目的や目標額によって、取るべきリスクも違います。「やった気になって、結局目標を達成できなかった」なんてことにならないように注意しましょう。
回避法:
- まずは「何年後に、いくら欲しいか」などの目的・目標を決める
- 目的達成から逆算して投資方法(インデックス投資、個別株など)を決める
余剰資金ではないお金を運用に回す
生活費や教育資金など、近い将来使う予定のあるお金を投資に回すと危険です。相場が下がったタイミングで急な出費が重なると、含み損のまま解約しなければならなくなります。
また、余剰資金ではないお金で投資するとメンタルがブレて、暴落時に売却したり、焦って投資しすぎて失敗します。資金の余裕=メンタルの余裕に繋がるので、必ず余剰資金で投資をしましょう。
回避法:
- まず生活防衛資金(6か月〜1年分の生活費)を現金で確保する
- 直近5年以内に使うお金は無理に投資しない
短期間で一気に資産を増やそうとする
「短期間で倍にしたい」と高リスクな投資に飛びつくのは危険です。値動きの激しい個別株や仮想通貨に大金を入れて大損するのは、典型的な失敗パターンです。
短期間で一気にお金を増やしたい気持ちはわかりますが、無茶な投資をしても損するだけなので慎重に判断しましょう。また、ハイリターンばかり追い求めていると詐欺に引っかかる可能性もあるので注意してください。
回避法:
- 資産形成は長期・積立・分散が鉄則です
- 短期的に増やしたい場合も大金は投資しない
口コミやSNSの噂だけで判断する
「インフルエンサーが勧めてたから」「みんなやっているから」といった理由で投資するのは危険です。中身が分からないまま契約してしまうと、大損する場合も多いです。
最近では、不動産クラファンをインフルエンサーが紹介していますが、絶対におすすめしません(詳細は下記をご覧ください)。
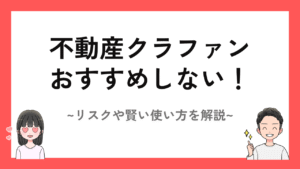
回避法:
- SNSの情報は話半分で見ておく
- 内容が理解できないものには投資しない
支出を把握していない
家計の収支が不明確なまま投資を始めると、途中で生活費が足りなくなり、積立を中止したり借金に頼ることになりかねません。
また、投資は資金量が重要なので、支出を把握して家計管理した方が効果が最大化できます。投資でお金を増やしたい人こそ、家計管理を徹底しましょう。
回避法:
- 家計簿アプリなどで毎月の支出を可視化する
- 通信費や保険、サブスクなど固定費を見直して余剰資金を増やす
公的保障を理解せず、保険の入りすぎる
不安から民間保険に入り過ぎると、毎月の保険料が資産形成の足かせになります。日本には健康保険や高額療養費制度、遺族年金など、意外と手厚い保障があります。
例えば高額療養費制度では、年収にもよりますが医療費の自己負担は月8~9万円程度で済む場合があります。他にも色んな保障があるので、まずは公的保障を理解しましょう(詳しくは下記をご覧ください)。
-1-300x169.png)
回避法:
- 公的保障をまず理解する
- 足りない分だけ民間保険(掛け捨て型)でカバーする
貯蓄型保険で運用も併用しようとする
「保険と投資が一度にできてお得」に見える貯蓄型保険は、実際には運用効率が低く、途中解約で大きな損をすることがあります。返戻率が100%を超えるまで10年以上かかることもあり、長期的にみると投資信託に劣ります。
資産形成の観点で見ると、保険は掛捨て一択です。保険屋に運用を任せる貯蓄型は、コストが高いので無駄が多いです。資産形成に成功している人で貯蓄型をしている方は少ないです。
回避法:
- 保険は保障、投資は投資で分けて考える
- 本当に必要な保険かしっかり考える
まとめ
投資でお金を増やしたいのに成果が出ない多くの原因は、特別な失敗ではなく初心者がついやってしまう9つのNG行動にあります。
- 銀行や保険会社の勧めをそのまま受け入れてしまう
- 目的を決めずに投資を始める
- 生活に必要なお金までリスク資産に入れてしまう
- SNSや口コミの情報を鵜呑みにする
これらはどれも「知らなかった」「よく調べなかった」から起きるものです。逆に言えば、目的を決め、家計を整え、余剰資金で長期・分散・低コストの投資をするという基本を守れば、大きな失敗はほぼ防げます。
特に初心者がまずやるべきは以下の3ステップです。
- 家計を把握し生活防衛資金を確保する
- 投資の目的と目標金額・期間を決める
- 低コストで分散できるインデックス投資から始める
これだけで、過剰な保険や高コスト商品、短期投機の罠から自然と距離を置けます。お金を増やすのはギャンブルではありません。シンプルな基本を知って、感情ではなくルールで動くことが何より大切です。今日からでも、自分のお金の流れと目標を整理して「失敗しない資産形成」を始めましょう。
他にもお得情報を発信しているので、ぜひ参考にしてくださいね!
私たちはお得と株が大好きなズボラ夫婦で、投資やポイ活情報など誰でもできる資産形成を発信中。お金を増やしたい、お得に生活したい人はぜひフォローしてね♪
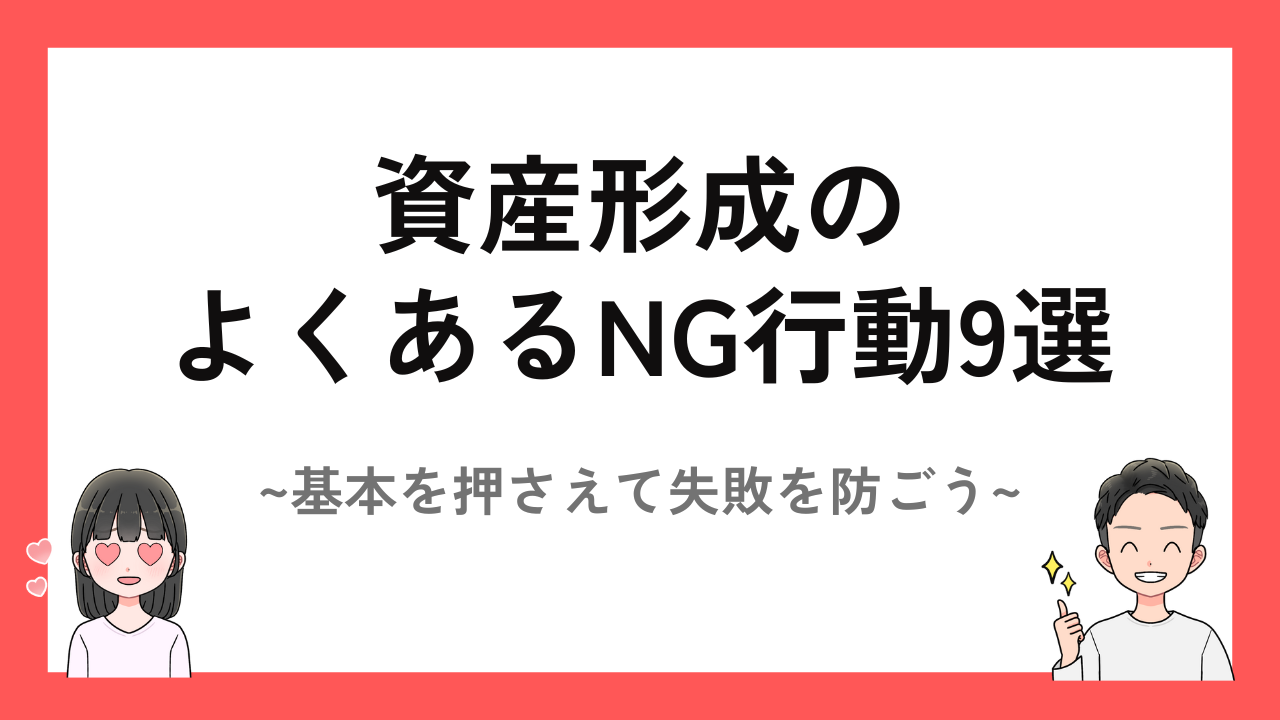
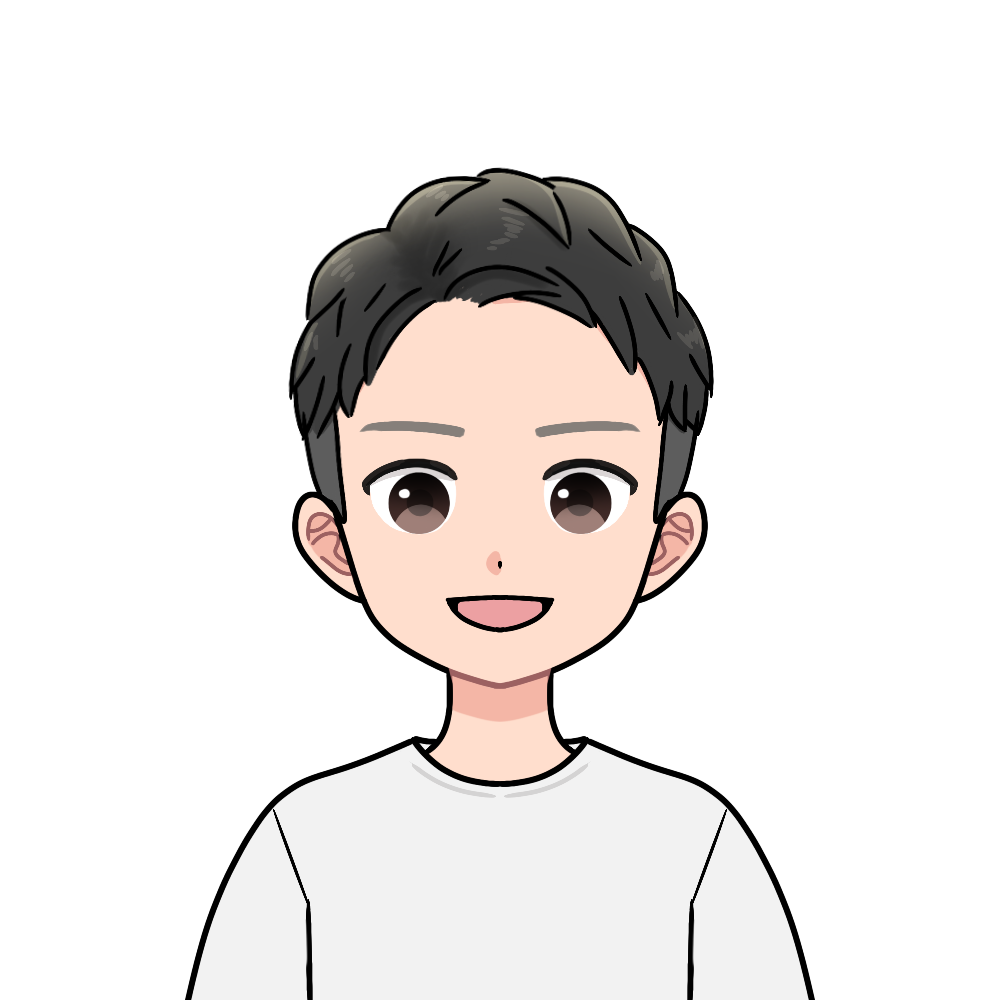
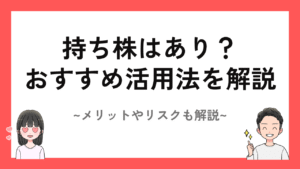
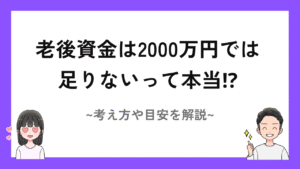
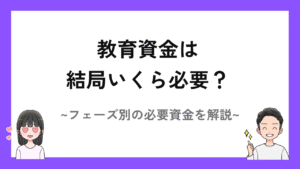
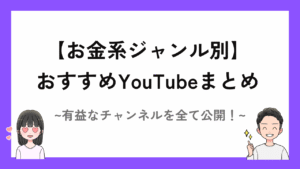
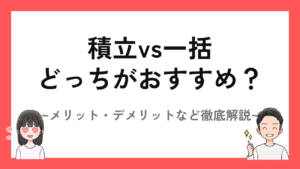
-2-300x169.png)