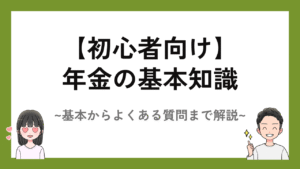毎月の給料から「所得税」「住民税」「社会保険料」が引かれているけれど、実はどうやって計算されているのか知らない…という人は意外と多いものです。
税金の仕組みを理解することで、手取りの仕組みが見えるだけでなく、将来の節税やお金の使い方にも差がつきます。
この記事では、社会人なら知っておきたい税金の基本の仕組みから自分でおおまかな税額を計算できるレベルまで詳しく解説していきます。
税金の基礎知識
日本で働く人が支払う税金や保険料は複数ありますが、毎月の給料から自動的に差し引かれている主なものは「所得税」「住民税」「社会保険料」の3つです。
それぞれの性質や仕組み、税率を正しく理解することで「なぜこんなに手取りが減るのか」「どうすればお金をうまく残せるか」が見えてきます。まずは基本的な内容と、税金に関わる申告の流れを解説します。
主な税金は所得税、住民税、社会保険料の3つ
気にかけるべき税金は主に所得税、住民税、社会保険料です。社会保険料は税金と呼ばれないですが、負担額は大きくリターンは小さいので実質的に税金と同じです。
他にも消費税や酒税、固定資産税など税金の種類は多いですが、節税などに繋がる上記3つを理解することから始めましょう。
所得税は所得に応じて5~45%
所得税は「所得の金額」に応じて段階的に税率が上がる累進課税制度が採用されています。税率は5%から始まり、所得が増えるごとに10%、20%…と増えていき、最大で45%です。
| 所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円まで | 5% | 0円 |
| 195万円 から 330万円まで | 10% | 97,500円 |
| 330万円 から 695万円まで | 20% | 427,500円 |
| 695万円 から 900万円まで | 23% | 636,000円 |
| 900万円 から 1,800万円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円 から 4,000万円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
よくある勘違いですが、所得金額とは額面年収ではありません。額面年収から様々な控除を引いたものが所得金額です。
また、税率は所得が330万円になるとすべてに10%かかると勘違いが多いですが、正しくは最初の195万円分は5%、次の135万円分(195~330万円の範囲を指します)は10%と段階的に計算します(1円超えたから急に税金が急増するわけではありません)。
ただし、段階的に計算するのは面倒です。そのため、税率を掛けた後に控除額を引くと答えが出るように設計されています。例えば、課税所得が400万円なら400万円×20%-427,500円=372,500円が所得税です。
所得税率はiDeCoなどの節税対策を考えるときに重要な要素です。iDeCoなら掛金が控除できるため、所得税率が33%など高い人ほど節税効果は高いのでiDeCo優先、5%と低ければ節税効果が低いのでNISAを優先しようと考えることが可能です。
住民税は一律約10%
住民税は、所得税とは異なり、一律で約10%です。所得税と同じく課税所得を算出した上で10%を掛けて計算します。
社会保険料は一律約15%(+会社が15%負担)
社会保険料には、健康保険・厚生年金・雇用保険などが含まれており、給料の約15%が天引きされます。本当は30%ですが、会社員の場合は会社と労働者で折半する仕組みなので15%に抑えられています。
自営業や任意継続者になると、全額を自分で支払う必要があるため、約30%の社会保険料を支払うことになります。。
基本は確定申告が必要
会社員は馴染みが無いと思いますが、原則は確定申告が必要です。ただし、各個人が確定申告する仕組みだと、わからない人や未申告者が続出するため、会社がまとめて申告する責任を負って代行してくれています(これを年末調整と呼びます)。
条件を満たすと確定申告が不要(年末調整のみでOK)
副業収入がない、医療費控除や住宅ローン控除の申告が無いなど年末調整で賄える場合は確定申告は不要です。年末調整と確定申告は名前が異なりますが、同じことです。確定申告の簡易版が年末調整で、年末調整で全て完結するなら追加で確定申告はしなくていい仕組みになっています。
ただし、給与以外に収入があったり、医療費控除や住宅ローン控除1年目など年末調整で申請できない場合は、自分で確定申告する必要があります。
基本を理解できるとメリットが大きい
税金の仕組みを知ることは、節税や無駄な税金を払わないなど資産形成に役立ちます。
- 節税できるポイントを見つけやすくなる
- 副業や独立時の資金計画が立てやすくなる
- 将来に向けた資産形成の土台ができる
税金の基本が理解できたところで、ここからは税金の金額が決まる流れや自分で計算できる方法を解説していきます。
税金が決まる流れ
税金の計算は、「収入 → 控除 → 税率 → 税額控除」の順に進んでいきます。会社員の場合、多くは年末調整で自動的に処理してくれますが、副業や控除申請がある人は自分で確定申告する必要があるので理解しておきましょう。
まず1年間(1月〜12月)でどれだけの収入があったかを計算します。ただし「収入」ではなく経費などを引いた「所得」です。
会社員 → 給与所得(年収から給与所得控除を引く)
フリーランス → 事業所得(売上から経費を引く)
「所得」から医療費や保険料、扶養家族などの控除を引きます。
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 扶養控除 など
税額そのものから引ける「税額控除」がある場合、ここで差し引きます。(所得控除と混同しやすいですが別です)
- 住宅ローン控除
- 配当控除
- 外国税額控除 など
次に計算に必要な所得と控除の種類について解説していきます。
所得の種類
税金を計算する上で、重要なのが「どんな種類の所得か」を把握することです。所得税はすべての収入に同じように課税されるわけではなく、所得の種類によって計算方法や控除の扱いが異なります。
| 所得の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 利子所得 | 銀行預金の利子、国債の利子など |
| 配当所得 | 株の配当、投資信託の分配金など |
| 不動産所得 | アパート経営や土地の賃貸など |
| 事業所得 | 個人事業主、副業の売上など |
| 給与所得 | サラリーマンの給料・賞与など |
| 退職所得 | 退職金など |
| 山林所得 | 山林の伐採・売却による収入 |
| 譲渡所得 | 株や不動産の売却益など |
| 一時所得 | 生命保険の満期金、懸賞金など |
| 雑所得 | 年金、副業、仮想通貨などその他の所得 |
株の税金は申告分離課税なので、所得税・住民税の計算には含みません。投資に関する税金については下記をご覧ください。
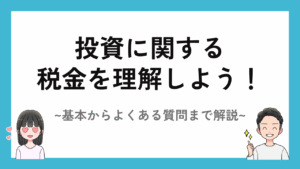
控除の種類
控除とは、「収入のうち、税金の対象から除ける金額」のことです。控除が多ければ多いほど、税金のもとになる「課税所得」が少なくなり、支払う税金も減ります。
| 控除名 | 対象となる人・条件 | 控除額の目安・内容 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 社会保険料を支払った人 | 支払全額 |
| 給与所得控除 | 給与所得者 | 年収に応じて一定額が自動的に控除される(参考:国税庁HP) |
| 基礎控除 | 全ての納税者 | 年収2,400万円以下なら48万円控除 |
| 配偶者控除 | 配偶者の年収が48万円以下 | 最大38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の年収が48万円超~133万円以下 | 最大38万円(所得に応じて変動) |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養家族がいる場合 | 一人あたり38万円~63万円(年齢等により異なる) |
| 生命保険料控除 | 生命保険加入者 | 掛金分(最大上限あり) |
| 医療費控除 | 医療費が年間10万円(または所得の5%)を超える場合 | 超過分が控除対象 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済・iDeCoなどの掛金を払っている場合 | 掛金の全額が控除対象 |
| 寄付金控除 | ふるさと納税などの対象団体に寄付した場合 | 寄付金から2,000円を引いた額が控除対象 |
よく使うのは、給与所得控除、基礎控除、配偶者控除、寄付金控除です。また、扶養控除や医療費控除、小規模企業共済等掛金控除も上手に使うと節税に繋がります。
自分の税金を計算してみよう
税金は「なんとなく引かれてる」ものではなく、自分で仕組みを理解すれば、節税もできます。ここでは、実際に自分の税金がどうやって決まっているのか、2ステップで整理してみましょう。
【STEP1】所得から控除を差し引く
会社員なら額面年収から社会保険料控除、給与所得控除、基礎控除を差し引きます。配偶者を扶養しているなら配偶者控除、両親を扶養しているなら扶養控除も差し引きます。
また、ふるさと納税をしたなら寄付金額-2,000円、iDeCoをした人は掛金全額を小規模企業共済等掛金控除として差し引きましょう。他にも医療費10万円超えた分や生命保険の支払いがあれば差し引いてください。
【STEP2】所得税と住民税を算出する
所得税は課税所得を下記表に当てはめ、住民税は課税所得の10%として計算します。
| 所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円まで | 5% | 0円 |
| 195万円 から 330万円まで | 10% | 97,500円 |
| 330万円 から 695万円まで | 20% | 427,500円 |
| 695万円 から 900万円まで | 23% | 636,000円 |
| 900万円 から 1,800万円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円 から 4,000万円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記の流れで自分の税金額がわかります。社会保険料と合わせると多い人で約50%を税金として支払っています。まずは現状を理解した上で、節税や賢い判断ができるようになるのでぜひ学び続けてくださいね!
よくある質問
参考動画
他にもお得情報を発信しているので、ぜひ参考にしてくださいね!
私たちはお得と株が大好きなズボラ夫婦で、投資やポイ活情報など誰でもできる資産形成を発信中。お金を増やしたい、お得に生活したい人はぜひフォローしてね♪
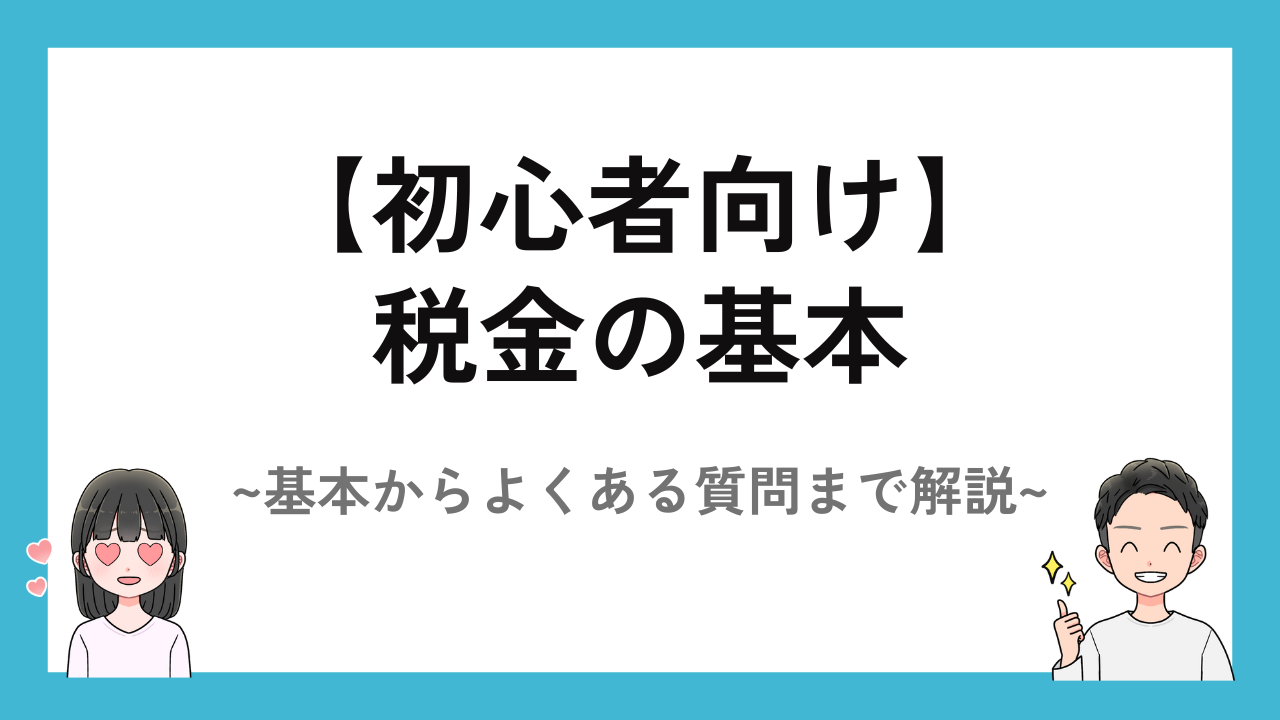
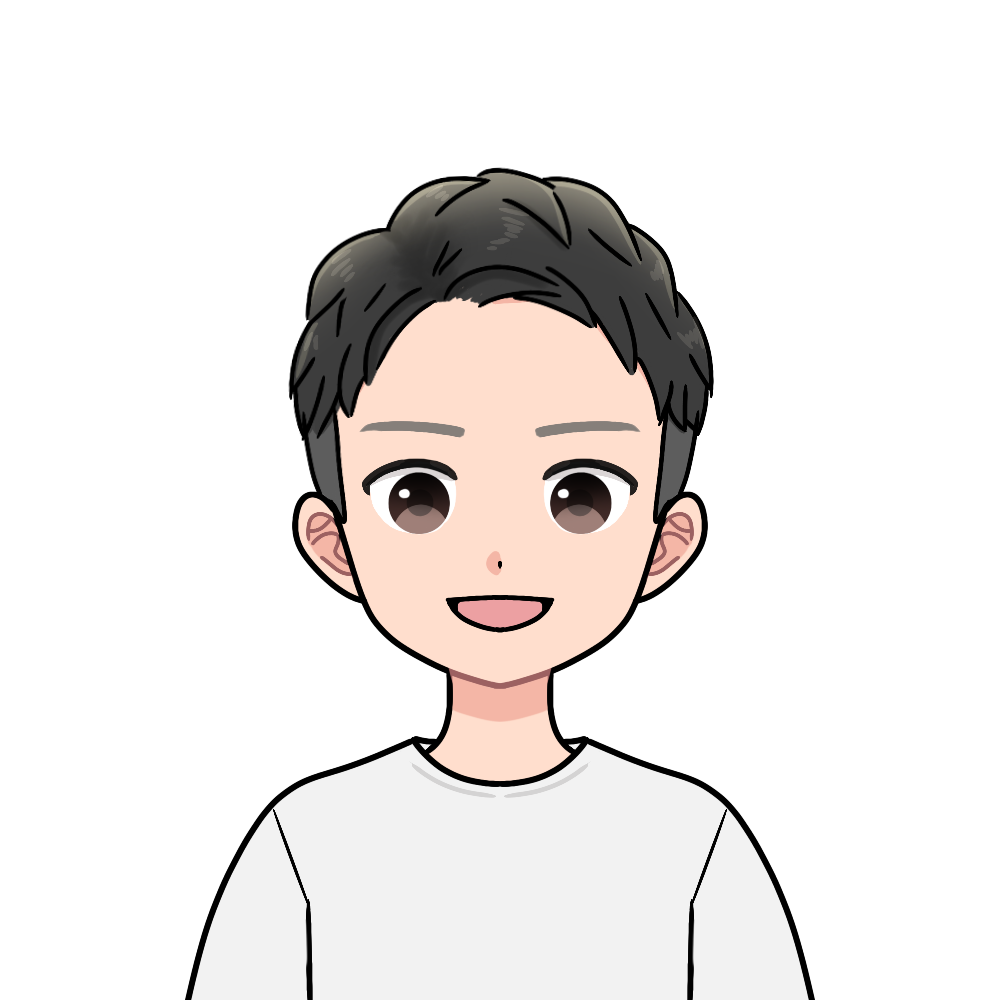
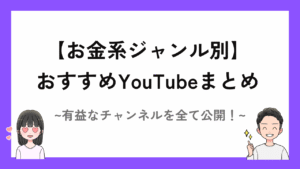
-2-300x169.png)
-1-300x169.png)
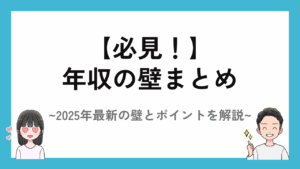
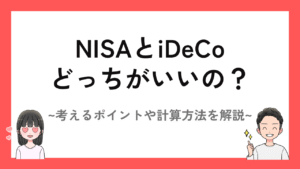
-300x169.png)